口、又は鼻より内視鏡を入れて食道、胃、十二指腸を体内から調べる検査です。
検査時間は5分から10分程度と短く(検査前の準備にはもう少し時間がかかります)、バリウム検査と違って実物を目で診ることが可能なため診断能力が非常に高い検査です。
また気になる病変があれば組織を一部採取する(生検と言います)ことが可能なのもバリウム検査との大きな違いです。
従来は口から内視鏡を入れていたので「胃カメラは辛い」という印象が強かったのですが、鼻から入れる内視鏡(経鼻内視鏡)が登場してからはそういった偏見は過去のものとなりつつあります。
経鼻内視鏡は胃カメラの患者様への負担を少しでも減らすために、口からではなく、鼻腔から入れることを目的として開発されました。
この先はわかりやすいようにQ&Aの形で説明いたします。
従来の口から入れる内視鏡の場合、舌の奥に内視鏡がどうしても触れてしまうため、「オエッ」という咽頭反射が起きてしまいます。
鼻から内視鏡を入れるとルート的に内視鏡が舌に触れることが無いので咽頭反射がほとんど起きず、非常に吐き気が生じにくいのです。
その結果、検査を楽に受けることが可能になります。
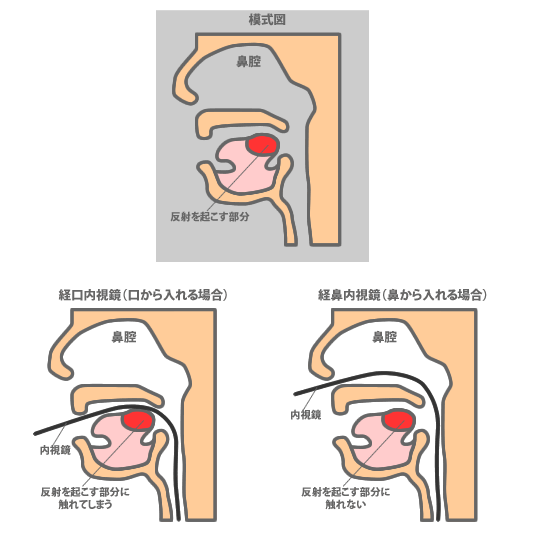
先ほど述べたように吐き気が生じにくいためと内視鏡が細いためです。
従来の口から入れる内視鏡の太さが10mm前後なのに対し、経鼻内視鏡は5.8mmと約半分の太さになるため単純に物理的に患者様への負担が小さくなる(細ければ細いほど患者様は楽になる)のです。
口から入れる内視鏡とは少し前処置(検査を受けるための準備)が異なります。
基本的な流れを箇条書きで示します。
1.消泡剤・胃粘液除去剤を服用する(胃の観察をしやすくする) ← 口からの内視鏡と同様です
2.両鼻腔に局所血管収縮剤を注入する(鼻の粘膜血管を収縮させることで出血を防ぎ、鼻の通りも良くします)
3.両鼻腔に局所麻酔薬を噴霧する(鼻の粘膜に対する表面麻酔です。内視鏡が通る時の苦痛を和らげます)
4.通りの良い方の鼻腔に局所麻酔薬を塗ったチューブを挿入する
(ほぼ内視鏡と同じ太さのチューブです。 鼻腔を拡張する効果があり、またこれを入れることで内視鏡が入るかどうかの確認ができます)
5.検査を開始します
口からの内視鏡よりも非常に楽なこと、検査中も話ができること(口からの内視鏡ではできません)が挙げられます
鼻腔が内視鏡よりも狭い人には検査ができないこと、そして血管が豊富で傷つきやすい鼻腔を内視鏡が通るため、鼻血が出ることがあります。
しかしほとんどの場合ごく少量であり、自然に止血されます。
また、経鼻内視鏡は口からの内視鏡よりも細いため解像度が若干低くなり、診断精度が少し低くなる(見落としが多くなる)とされてきました。
しかし技術の進歩により経鼻内視鏡の解像度も飛躍的に向上し、現在では早期胃癌の発見率でも口からの内視鏡と変わらないという報告が増えてきています。
鼻腔が狭くて内視鏡が通らない人以外は誰でも受けられますし、鼻腔が狭い場合は同じ内視鏡を使って口から検査を行うことも可能です(口からでも通常の内視鏡よりも細いので楽に検査が受けられます)。 前処置により多少の違いはあるかもしれませんが、検査の費用はほぼ同じです。



